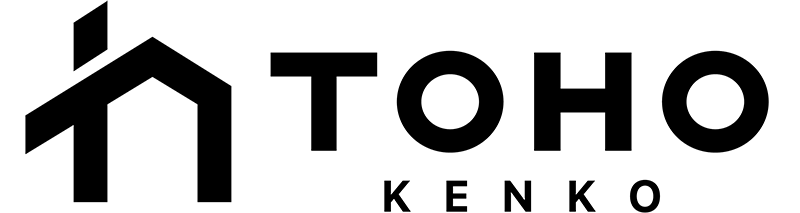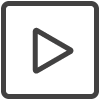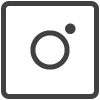注文住宅の土地購入の流れを解説|売買契約の進め方や注意点、税金や諸費用など、土地探しのお役立ち情報満載!
Contents
注文住宅を建てる第一歩となる土地購入。複雑な手続きや専門用語に戸惑うことも多く、どのような流れで進んでいくのか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、「買付け」「契約」「引渡し」という3つのステップに分け、土地購入の基本的な流れをわかりやすく解説します。また、契約時の注意点、諸費用や税金のこと、土地購入後の大まかなステップなど、マイホーム完成までのポイントも紹介します。夢のマイホームの実現に向け、この記事をぜひご活用ください。
注文住宅の土地購入の基本的な流れ3ステップ【買付け・契約・引渡し】
注文住宅を建てるには、まず土地を購入する必要があります。土地購入は高額な取引となるため、慎重に進めることが大切です。この章では、土地購入の基本的な流れを「買い付け(購入申込)・契約・引渡し」の3ステップに分け、それぞれの段階で必要な手続きや注意点を詳しく解説します。
(1)買付け(購入申込)
土地探しにおいて、気になる土地を見つけたら、買付けの手続きへと進みます。この段階では、購入希望の意思を売主に伝えるための手続きや、住宅ローンの事前審査などが必要です。
情報収集と土地探し
理想の土地を見つけるためには、事前の情報収集が不可欠です。希望条件の優先順位を家族で話し合い、予算オーバーしたときや希望に合う土地が見つからないときに、妥協してもよいポイントを決めておきましょう。
また、気になった土地の現地確認は時間帯を変えて複数回行い、周辺環境、騒音、日当たり、風通しなどを自分の五感で確かめるのがおすすめです。近隣の方に話を聞いてみるのも有効です。
併せて、自治体の発行するハザードマップで水害、土砂災害、地震などの災害リスクを確認します。地盤の強度が気になる場合は、専門業者に地盤調査を依頼しましょう。
買付証明書(購入申込書)の提出
希望に合う土地が見つかったら、購入の意思表示として、売主または仲介した不動産会社に買付証明書(購入申込書)を提出します。買付証明書には、購入希望金額、物件情報(所在地、地番、面積など)、買主情報、支払方法、買付けの有効期限などを記載します。
買付証明書には法的拘束力がないため、提出後に撤回することも可能です。ただし、売主が契約の準備を進めているにもかかわらずキャンセルすると、損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。
人気の土地は複数の購入希望者がいることも想定し、提出後の手続きをスムーズに行えるよう準備しておきましょう。
住宅ローンの事前審査
土地購入代金の支払いに住宅ローンを利用したい場合は、このタイミングで事前審査を受ける必要があります。
通常の住宅ローンは建物完成が融資実行の条件となるため、土地購入費用や先行費用をローンで賄うには、土地先行融資やつなぎ融資の利用を検討する必要があります。金融機関に事前審査を依頼し、希望額を借り入れられるか確認しましょう。
事前審査に必要な書類(収入証明書、本人確認書類など)はあらかじめ準備しておき、スムーズな手続きを心がけることが大切です。また、事前審査の時点で、大まかな建物プランや概算見積りも必要になるため、土地探しと並行してハウスメーカーや工務店などの住宅会社に相談するのも忘れないようにしましょう。
(2)契約
買付証明書を提出し、住宅ローンの事前審査も通過したら、正式な契約締結へと進みます。契約は法的拘束力を持つため、内容をしっかりと確認したうえで結ぶことが大切です。
手付金の支払い
契約時には、通常土地価格の5~10%程度を手付金として支払います。この手付金は、売買契約が成立した証拠金となります。手付金は現金で支払うケースが多いため、金額を事前に確認して手元に準備しておきましょう。順調に契約が進めば、手付金は土地代金の一部に充当されます。
なお、不動産会社の仲介で土地を購入する場合は、仲介手数料の半額を契約時に支払うのが一般的です。
重要事項説明と土地売買契約締結
契約締結前に、宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。重要事項説明では、土地の権利関係、法令上の制限、境界線、インフラ設備など、土地に建物を建てるにあたって重要になるポイントを確認します。説明内容を完全に理解できるよう、疑問点はその場ですべて解消しておきましょう。
また、手付金や違約金に関する規定、契約解除の条件、固定資産税・都市計画税の精算方法、土地代金の支払期日などもチェックします。
重要事項説明を受けて問題がなければ、土地売買契約の締結へと移ります。契約書には印紙を貼付し、2通の原本を売主・買主で1通ずつ保管するというのが基本です。
ただし売主が不動産業者の場合、1通を作成し原本を買主・写しを売主が保管する場合もあります。
住宅ローン本審査とローン契約締結
売買契約の締結後、住宅ローンの本審査に進みます。本審査は事前審査よりも詳細な審査となり、上記の売買契約書や登記事項証明書も必要になります。加えて、建築プランや最終的な見積りの提出が求められるため、住宅会社とプランを詰めておきましょう。必要書類を確実に準備し、金融機関の指示に従うことが、スムーズな手続きのポイントです。
追加書類の提出を求められる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします。
本審査を通過したら、金銭消費貸借契約書(ローン契約書)の内容を確認し、実印で記名押印のうえ締結します。保証会社を利用する場合は保証委託契約も締結して、ローン関連の手続きが完了となります。
(3)引渡し
契約が完了し、住宅ローンの本審査も通過したら、土地の引渡しとなります。所有権移転登記などの手続きを行い、手付金を除く残金を決済します。
残金の支払い
残金は現金で支払うのが基本であるものの、売主が承諾すれば口座に直接振り込むことも可能です。金融機関に依頼すれば、自分の口座を通さずに手続きできる場合もあります。
先に支払った手付金が購入費用の一部に充当されるため、その分を差し引いた金額を売主へ支払います。当日の支払方法、振込手数料の負担などは事前に確認しておきましょう。
融資実行・残金決済・引渡しを同日に行うケースが多いため、日程や場所などは金融機関、売主と調整します。仲介を利用したときは、不動産会社が中心となって調整するのが一般的です。
所有権移転登記・引渡し
土地の所有権が売主へ移ったことを示す所有権移転登記や、融資する銀行の権利を示す抵当権設定登記は、司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。司法書士への報酬、登録免許税の支払いが発生するため、事前に準備しておきましょう。
売主から権利証などを受け取れば、晴れて土地が自分たちの所有になります。なお、固定資産税・都市計画税は年1回納付であり、その年の1月1日時点の所有者に対して課税される仕組みです。買主が1年分をまとめて納めることになるので、引渡し後にかかる分に関しては、日割り計算で売主へ支払う必要があります。
土地の売買契約を締結する際の3つの注意点
土地の売買契約は法的拘束力を持つため、後のトラブルを防ぐためにも、しっかりと内容を確認したうえで取り交わす必要があります。ここでは、土地の売買契約を締結する際に注意すべき3つのポイントを解説します。
(1)契約内容を事前にくまなく確認する
契約書は、売買価格、土地面積、引渡し日といった基本事項はもちろんのこと、登記事項証明書の内容と一致しているかなど、細かく確認しましょう。契約解除に関する条項や特約事項の内容を理解することも大切です。
特に住宅ローンが承認されなかった場合に、無条件で契約解除できる旨を定めた「ローン特約」は買主にとって重要な項目です。
付帯設備(浄化槽の設置義務や私道負担の有無など)やインフラ整備状況(上水道・下水道・ガス・電気が引き込まれているか、プロパンガスか都市ガスかなど)も確認しておきましょう。これらの項目は、今後の建築費用や生活に影響を与える可能性があります。
契約内容をくまなく確認しておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。
(2)重要事項説明で疑問や不明点を解消する
重要事項説明は、売買契約締結前に宅地建物取引士から行われます。説明内容は土地の権利関係(所有権、抵当権の有無など)、法令上の制限(建ぺい率、容積率など)、境界線、インフラ設備の有無と種類、災害リスクなど多岐に渡ります。
重要事項説明の内容は、専門用語が多く、難解に感じることもあるでしょう。しかし、不明点は積極的に質問し、納得いくまで確認することが大切です。いずれも、その後の建築や生活に大きく関わる内容なので、疑問や不安を残したまま契約を締結しないようにしましょう。
重要事項説明書は事前にコピーをもらえる場合が多いので、先に内容を熟読し、疑問点をリストアップしておくとスムーズに説明を受けられます。
(3)手付金や違約金について確認する
一般的に物件価格の5~10%を、手付金として契約時に支払います。手付金の支払い時期や契約解除時の返金条件、買主都合による契約解除時の違約金の有無や金額、売主都合による解除の場合の取り決めなどを事前に確認しておきましょう。
万が一の事態が発生したときのリスクを把握し、適切な対応ができるように備えておくことが大切です。手付金の保全措置についても確認しておくと、より安心して取引を進めることができます。例えば、売主が破産・倒産した場合などに備え、手付金を保全する制度があるため、その有無や保全の方法について売主や不動産会社へ確認しておくと安心です。
土地購入にかかるお金のこと|諸費用や税金の種類と目安
土地購入に際してはさまざまな諸費用がかかります。諸費用は土地の価格や、住宅ローンの利用有無などによって変動します。あらかじめ何がいくらくらいかかるのか把握し、資金計画に盛り込んでおかないと、予算オーバーになる恐れがあるため要注意です。
諸費用は土地購入費用の5〜10%が目安
土地購入にかかる諸費用は、一般的に土地代金の5〜10%程度が目安となります。例えば、2,000万円の土地を購入する場合、100万円〜200万円程度の諸費用が見込まれます。
諸費用は、土地の状況や住宅ローンの有無によっても変動します。住宅ローンを利用するなら融資手数料や保証料が発生するほか、土地の状態によっては地盤改良費用(測量費用は通常売主負担)、古家が残っている場合には解体費用が必要になるでしょう。
諸費用の多くは、原則として自己資金で負担するため、一定の現金を準備しておく必要があります。自己資金不足であれば、諸費用も含めたローンの借り入れを検討しましょう。
諸費用の内訳と項目ごとの金額目安
諸費用の主な項目と金額の目安を以下の表にまとめました。
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 土地価格×3%+6万円+消費税(土地価格400万円以上の場合の上限) | ハウスメーカーや工務店などから直接購入する場合など、不動産会社の仲介を受けない場合は不要 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×税率(軽減税率:2026年3月31日まで1.5%、本則税率2%) | 土地の所有権移転登記にかかる税金 |
| 印紙税 |
不動産売買契約書は軽減税率が適用(2027年3月31日まで) ・契約金額1,000万円超5,000万円以下:1万円 ・契約金額5,000万円超1億円以下:3万円 |
売買契約書に印紙を貼付して納める税金 |
| 司法書士報酬 | 10万円前後 | 登記手続きを司法書士へ依頼する際の報酬 |
| 住宅ローン関連費用 | 手数料や保証料は金融機関によって異なる | 事務手数料、保証料、印紙代、抵当権設定登記の登録免許税など |
| 解体費用 | 建物の構造や面積による | 古家がある場合に発生する費用 |
| 地盤改良費用 | 土地の状態や工法による | 軟弱地盤で補強が必要な場合に発生する費用 |
|
上下水道・電気・ガスの 引き込み費用 |
引込む長さによる | インフラ整備が必要な場合に発生する費用 |
| 農地転用費用 | 10~20万円程度 | 農地を新たに宅地として活用する場合にかかる費用 |
これらの費用以外にも、予期せぬ費用が発生することもあります。余裕を持った資金計画を立て、想定外の事態にも対応できるようにしましょう。
土地購入後の流れ|着工から引渡しまでの7ステップ
土地を購入したら、いよいよ家づくりがスタートします。着工から引渡しまでには、どのようなステップがあるのでしょうか。ここでは、土地購入後の流れを7つのステップに分けて解説します。
(1)建築プラン・見積りの確定
土地を購入したら、施工を依頼する住宅会社と綿密な打ち合わせを行い、希望に沿った建築プランを決定します。プランが確定したら、それに基づいて詳細な見積もりを作成してもらい、最終的な建築費用を確認しましょう。建築プラン、図面、見積りが出そろったら、金融機関に住宅ローンの本審査を申し込みます。
(2)建築工事請負契約の締結
建築プランと見積もりが固まり次第、施工を依頼する住宅会社と工事請負契約を締結します。契約内容(工事内容、金額、工期、支払い方法など)を綿密に確認し、不明点や疑問点は必ず解消しておきましょう。特に、代金支払いのタイミングと各回の金額は、資金計画に大きく影響するため、認識に違いがないか十分なチェックが必要です。
(3)詳細プラン決定と建築確認申請
工事請負契約を締結後、内外装、設備などの詳細な仕様を決定します。床材、壁紙、キッチン、浴室など、さまざまな選択肢の中から、理想の住まいをイメージして選んでいきましょう。
詳細プランが決定したら、施工会社が建築確認申請を提出します。建築基準法上問題のない旨が認められ、確認済証が交付されると、いよいよ着工が可能になります。
(4)地盤調査の実施
地盤調査は、建物の安全性を確保するために大切な工程です。現行の耐震基準である「2000年基準」により、木造住宅建築時の地盤調査が実質的に義務化されています。調査結果に基づき、地盤の強度に応じた適切な基礎工事方法を選ぶことになります。地盤が軟弱な場合、地盤改良工事の費用負担が発生するため注意が必要です。
(5)着工・挨拶回り
着工前に、近隣の方への挨拶回りを済ませておきましょう。工事期間中の騒音や振動、車両の出入りなどでご迷惑をおかけすることを伝え、理解と協力を得ることが大切です。地鎮祭を実施する場合は、祭事終了後に、施工会社の担当者と挨拶回りを行うと良いでしょう。
近隣住民と良好な関係を築いておくと、円滑に工事を進められるだけでなく、住み始めてからのトラブル防止にもつながります。
(6)竣工・完了検査
工事が完了したら、完了検査を受けます。検査では、建築基準法に基づいて、建物の構造や設備が適切に施工されているかを確認。検査結果に問題がなければ、検査済証が発行されます。
また、施主立ち会いのもとでの竣工検査も行いますので、プランや要望が反映されているかを入念にチェックしましょう。施工ミスや改善点がある場合は、この時点で漏れなく指摘します。
(7)引渡し
竣工検査で指摘した事項がすべて改善されたら、いよいよ引渡しとなります。住宅ローンを利用する場合、このタイミングで残りの融資が実行されるので、残金を決済して鍵を受け取ります。建物の所有権保存登記と抵当権設定登記を行えば、マイホームの完成です。
長野・松本・上田エリアで土地購入の流れをスムーズに進めたいなら東邦建工へご相談を!
注文住宅を建てるための土地購入は、大きく「買付け(購入申込)」「契約」「引渡し」の3つのステップで進みます。売買契約書を締結した時点で法的拘束力が発生するため、それまでに疑問点や不安点を解消しておくことが大切です。
土地購入をスムーズに進めるには、その後の建築に関することも想定しておく必要があります。そのため、土地探しの段階からハウスメーカーや工務店に相談しておくのがおすすめです。地元密着型の会社なら、地元の土地情報にも精通しているため、不動産会社を介さずに理想の土地を見つけられる可能性もあります。
長野・松本・上田エリアで長年家づくりを手がけてきた東邦建工は、土地探しから資金計画のサポート、設計・施工、アフターサービスまでワンストップサービスを提供しています。建築条件付き土地の紹介もでき、少ない手間で理想の土地と住まいを実現することも可能。
グループ会社の東邦商事が売主となる土地を多数所有しており、建築条件付き土地のご案内もできます。なお、当社所有の土地をご購入いただく場合は仲介手数料がかかりません。
少ない手間で理想の土地にマイホームを建てたい、諸費用をできるだけ抑えたいという方はぜひ東邦建工にご相談ください。
監修者:間 雅博(はざま まさひろ)/宅地建物取引士