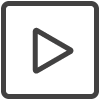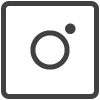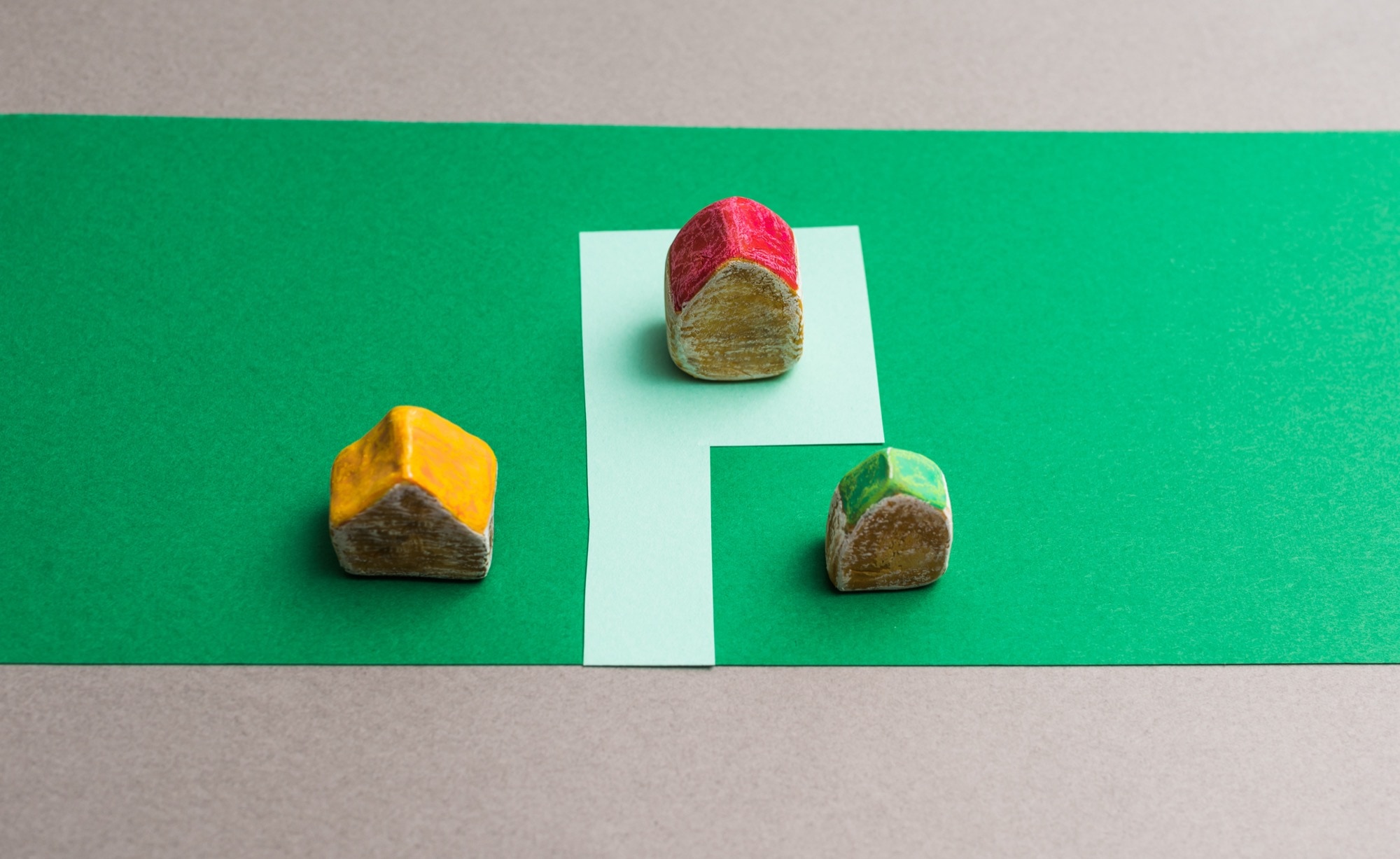土地選びの優先順位はどうする?注文住宅の土地の条件で重視すべき5つのポイントを解説!
Contents
注文住宅を建てる際、どのような土地を選ぶかは家づくりの成功を大きく左右します。理想のマイホームを実現するためには、条件に合った土地を見つけ出すことが欠かせません。
とはいえ、すべての条件を満たす土地を見つけるのは困難に近いため、土地選びの優先順位を明確にし、優先度の高い条件を満たす土地を選ぶことが大切です。
この記事では、注文住宅の土地選びにおける優先順位の決め方や、土地の条件で重視すべきポイントを解説します。土地購入からの注文住宅を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
土地選びの優先順位の決め方3ステップ
魅力ある理想の暮らしを実現するためには、土地選びの優先順位を明確にすることが重要です。以下では、優先順位の決め方を3つのステップでわかりやすく解説します。
ステップ1:理想の暮らしを具体的にイメージ
土地選びは、理想の暮らしを明確にイメージすることから始まります。「いい家に住みたい」という漠然とした考えではなく、家族構成やライフスタイル、将来のビジョンを踏まえて、どのような暮らしを実現したいのかを具体化しましょう。
まず、現在の家族構成や生活スタイルを分析し、生活の満足点・不満点を洗い出します。例えば、子どもが小さいなら広い庭がほしい、通勤時間が長ければ、駅近立地にしたいなどのニーズが見えてきます。また、将来のライフステージの変化を見据え、必要な住まいを考えることも重要です。
自分たちが家を建てる目的や大切にしたい価値観を明確にすることで、土地選びの軸を定められます。
ステップ2:譲れない条件と妥協できる条件をリストアップ
理想の住まいをかなえる土地を探すには、自分たちの譲れない条件と妥協できる条件を明確にすることが大切です。
まず、交通アクセス、周辺環境、広さ、日当たり、地盤など、自分たちの理想に合う条件をリストアップしましょう。そのなかから、暮らしへの影響が大きいものなど、絶対に譲れない条件を3~5つに絞り込みます。
一方で、土地の広さや形状、築年数など、予算に応じて柔軟に見直す「妥協できる条件」も検討しておきましょう。これにより、予算オーバーが生じたり、条件を満たす土地がなかなか見つからなかったりしても、スムーズに決断ができます。
ステップ3:家族で話し合って優先順位を決定
土地選びの条件の優先順位は、時間をかけて家族全員で話し合い、納得できる結論を目指すことが大切です。
まず、各自が「譲れない条件」と「妥協できる条件」をリストアップし、それらを共有することで家族全体のニーズを把握します。例えば、父親が通勤の利便性を優先する一方、母親は静かな環境を重視するといったこともあるでしょう。
次に、共有した条件をもとに話し合い、「予算」「立地」「広さ」などの優先順位を決定し、妥協点を探ります。
時間をかけても意見がまとまらないときや判断が難しいときは、不動産会社や住宅会社などの専門家に相談しながら整理するのも有効です。専門家の客観的なアドバイスを受けることで、新しい観点が得られ、より満足度の高い土地選びができるでしょう。
注文住宅の土地選びの優先順位決めで重視すべき5つのポイント
上述のとおり、注文住宅の土地選びでは、希望条件の優先順位を明確にすることが大切です。「予算」「立地・周辺環境」「土地の形状・広さ」「法規制」「防災リスク・地盤」の5つのポイントを重視すると、優先順位を決めやすくなります。
(1)予算
土地選びの前に、まずは予算を正確に把握しておきましょう。土地購入費用だけでなく、仲介手数料や印紙税、登記費用といった諸費用、さらに建築費用や外構費用まで含めた総予算を見通しておく必要があります。
これに加え、固定資産税や都市計画税といった税金や、将来のリフォームにかかる費用などの維持管理費用も考慮することで、無理のない資金計画を実現できます。
また、住宅ローンを利用する場合は、事前に金融機関で相談したり、WEB上のシミュレーションを活用したりして、借入可能額や毎月の返済可能額を把握しておきましょう。綿密な資金計画を立てることで、購入後も安心して暮らせる家づくりが可能になります。
(2)立地・周辺環境
毎日の暮らしを快適にするためには、職場や学校への交通アクセスが良好な土地を選ぶのがおすすめです。交通アクセスの良さを判断するため、最寄り駅までの距離や主要駅への所要時間、通勤時間帯の道路の混雑状況などを確認しましょう。通勤や通学に無理のない環境は、日々の生活の質を大きく向上させます。
さらに、スーパーやコンビニ、専門店、病院、銀行、郵便局、役所など、生活に必要な利便施設が近くにあるかどうかも大切なポイント。子育て家庭では、学校などの教育施設、保育園の位置もチェックしておきたいところです。
地域の治安状況や騒音の有無、隣人関係のトラブルの可能性、嫌悪施設(ゴミ処理場や工場など)の存在も細かくチェックしておくと、住み始めてから後悔するリスクを減らせます。
物件資料や担当者の説明だけではわかりづらい部分もあるので、できれば現地へ実際に見に行くのがおすすめです。
(3)土地の形状・広さ
建物を建てるにあたっては、土地の形状や広さが設計プランに大きく影響します。希望する家の間取りや延床面積を実現できる広さがあるかを確認し、将来的な家族構成やライフスタイルの変化も見据えた土地選びを心がけましょう。
また、土地の建ぺい率や容積率、前面道路の整備状況などをチェックすることで、建築可能な建物の規模や範囲を把握できます。接道面が狭い旗竿地などの場合、設計に制約が生じることもあるので注意が必要です。
家を建てたあとの使い勝手も考慮し、庭や駐車場、駐輪場などを設けるための場所も確保しましょう。さらに、プライバシーやセキュリティに配慮した配置計画を立てることで、安全で快適な住環境を実現できます。
(4)法規制
土地には、法令で定められたさまざまな規制があるため、事前に確認することがとても大切です。用途地域によって建築可能な住宅の種類が異なり、建ぺい率や容積率、道路斜線制限、北側斜線制限といった規制は建築プランに大きな影響を及ぼします。
また、セットバックが必要な土地の場合、実際に建物の敷地として使える面積が減少してしまうため注意が必要です。建築計画に支障が出ないよう、購入前にこれらの条件をしっかり確認しましょう。
土地探しの際には、家づくりの専門家である住宅会社に相談するのがおすすめです。家づくりのプロによるアドバイスを受けることで、上記のような法規制のリスクを未然に防ぎ、安心して土地を選ぶことができます。
(5)災害リスク・地盤
家族の安全を守るためには、土地のある場所の災害リスクや地盤の状況を事前に把握する必要があります。まず、自治体が発行するハザードマップを確認し、水害や土砂災害、地震などのリスクの大きさを調べましょう。加えて、災害時の避難経路や避難場所を確認しておくことも大切です。
とりわけ地盤の強さには要注意です。木造住宅の新築にあたっては、実質的に地盤調査が義務付けられています。調査の結果、地盤が軟弱な場合には地盤改良工事が必要になり、建築費用が大幅に増加するリスクがあるので注意しましょう。
さらに、液状化や不同沈下のリスクにも注意を払うべきです。地盤調査の結果に基づいて適切な対策を講じることで、安全で安心な住まいを実現することが可能です。ただし、これもコストがかさむ要因になります。
土地選びの優先順位を決める際に意識したいポイント
土地選びの優先順位を決めるにあたっては、どのようなことを意識すればいいのでしょうか。次に、優先順位決めを適切に行い、後悔のない家づくりを実現するためのポイントを紹介します。
絶対に譲れないNG条件を明確にする
土地選びでは、譲れない項目を明確にし、土地選びの軸を定めることが不可欠です。
希望条件をすべて満たす土地は基本的に存在しないため、どこかで何かしら妥協しなければなりません。このとき、譲れない条件を優先することによる消去法が有効です。例えば、共働き家庭であれば「職場からのアクセスが悪い」「周辺にスーパーがない」といった項目がNGとなりやすいでしょう。
NG項目をリストアップし、優先順位を付けることで、土地選びの流れがスムーズになります。希望条件の充足率が6〜7割でも、NG条件に該当しなければ購入を前向きに検討するという視点も大切です。
将来のライフプランの変化を見据える
土地選びでは、数年先だけでなく、子育てや子どもの独立、将来の介護といったライフステージの変化を見据えた検討が求められます。長い間住み続ける可能性を考え、将来のニーズにも対応できる土地を選ぶことで、家族の暮らしが変化しても快適性を保てます。
例えば、部屋を増やしたり増築したりできる広さのある土地や、車なしで生活が可能な利便性の高いエリアの土地などが選択肢に挙がるかもしれません。長期的な視点で土地を探すことが、将来にわたって後悔しない家づくりにつながります。
情報収集とプロへの相談を積極的に行う
理想の土地を見つけるには、幅広い情報収集と専門家への相談が不可欠です。インターネットの物件ポータルサイトや住宅情報雑誌の活用はもちろん、住宅会社の展示場やモデルハウスの見学、完成見学会への参加など、現地・現物による情報収集も大切です。
不安な点があれば、早めに不動産会社や住宅会社のスタッフへ相談し、疑問を解消しておきましょう。特に、住宅会社は選ぼうとしている土地に理想の家を建てられるかどうかなど、建築的な観点も踏まえたアドバイスを提供してくれるため、土地選びに安心感が生まれます。信頼できる専門家の意見を取り入れながら、納得のいく土地探しを進めましょう。
土地選びで実際によくある3つの失敗例と回避する方法
注文住宅では土地選びが大切ということを理解していても、失敗して後悔する例も少なくありません。ここでは、よくある3つの失敗例を挙げ、それぞれ回避するための方法を解説します。これを参考に、後悔のない土地選びを目指しましょう。
失敗例1:予算オーバーで理想の住まいをかなえられない
土地価格に気を取られ、建築費用や諸費用を見落とした結果、予算をオーバーしてしまうというのはありがちな失敗です。なかには、購入した土地に地盤改良工事が必要であることが判明し、想定外の追加費用が発生するといったこともあります。このような資金計画の甘さは、後悔を招く大きな原因となります。
回避する方法
予算オーバーを防ぐには、土地購入費用だけでなく、仲介手数料や印紙税、登記費用などの諸費用を含めた総予算を明確にすることが重要です。
また、土地購入費用・建築費用・諸費用の予算配分を早い段階で決定し、土地探しと並行して住宅会社に費用の見積もりを依頼しましょう。プロの意見を取り入れることで、適切な予算配分のもと資金計画を立てられます。
失敗例2:住環境の問題を見落としていて暮らし始めてから後悔する
新居での生活を始めてから、「日当たりが悪い」「騒音が気になる」「風通しが良くない」といった住環境の問題に気づき、後悔することがあります。また、近隣トラブルや治安の悪さ、通勤や買い物の利便性が不足している場合、日々の生活でストレスがたまりやすくなります。
回避する方法
住環境での失敗を防ぐには、気に入った土地が見つかったとき、異なる時間帯(昼と夜)、天候(特に雨の日)で現地を訪れ、状況を複数回確認することが大切です。
その際、近隣住民に直接話を聞いたり、地元密着の住宅会社や不動産会社に相談したりして、地域情報を収集しましょう。多角的に情報を集めることで、事前には気づきにくい住環境の問題を明らかにできます。
失敗例3:土地の法規制によって希望していたプランが実現できない
土地の法規制を十分に確認しないまま購入してしまい、希望する間取りや建築プラン、デザインを実現できないケースもあります。購入後に建ぺい率や容積率、斜線制限などの制約に直面し、理想の住まいを諦めざるを得なくなることもあるでしょう。
回避する方法
購入前に建ぺい率や容積率、道路斜線制限などの法規制を十分に確認し、土地の条件が自分たちの希望する建築プランやデザインに合致しているかを確認しましょう。
判断に専門知識を要する場合は、地元事情に詳しい住宅会社や不動産会社に相談することをおすすめします。経験豊富なプロのサポートを受ければ、土地の法規制によるリスクを回避できる可能性が高まります。
東邦建工は土地探しから全力でサポート!長野・松本・上田エリアでの家づくりはご相談を!
希望条件をすべて満たす土地を見つけるのは困難だからこそ、条件に優先順位をつけ、現実的な目線で土地選びをすることが大切です。ライフスタイルや将来のライフステージの変化を踏まえた優先順位づけをすれば、満足度の高い土地探しを実現できるでしょう。
東邦建工では、土地購入からの家づくりをトータルでサポートしています。家づくりの全体像を把握したうえでの土地探しが可能なため、お客様の優先順位や予算に適した土地を購入できるでしょう。
長野・松本・上田周辺の地域密着で家づくりを続けてきた実績があるので、魅力ある好立地な土地を見つけやすいのも強みです。同エリアで土地購入からの家づくりを検討しているなら、経験豊富な東邦建工までぜひご相談ください。
監修者:間 雅博(はざま まさひろ)/宅地建物取引士